写真はどこまでが「写真」なのか? 何の材料も無く考えることは困難だ。作家の試みを介して変成・拡張された「写真」の姿に触れ、その可能性を知る。

「写真」のように見えない写真もいつしか「写真」だなと自然に受け容れるようになっていたが、2010年代はそういう変革・拡張の時期だったのだろう。写真もといあらゆる画像、動画がデータとして扱われ、スマホ、編集アプリ、SNS、インターネット回線強化で急速に双方向送受信と誰でも加工が実現した。
長らく絵画の似姿をとるよう振舞ってきた「写真」は情報化された実生活の面からも「データ」として再定義されていて、たとえ目に見えなくてえも像が無くてもプリントを引き裂いても丸めても打ち捨てても宙に浮いていても、それが「写真」であると誰かが同意し流通する限りは定義の更新が成立、「写真」と呼ぶことが可能となる。だが旧来の絵画的な様式美と威厳を湛えた写真プリントの力も全く有効で、作品として鑑賞するにはそちらの方が強いだろう。体験の量と慣れでは後者の方が遥かに上だからだ。
要は現在の写真は多様性と固定解に引き裂かれている。どちらもが正解である。
本展示はそんな現代にふさわしく、4名の作家が写真の様態、姿形、定義について、大胆に拡張し変容を試みる。非決定的な暫定の「現在」形である。「現在」は今後もずっと更新され、その都度、写真と私達が取り結ぶ認識の契約内容は更新されてゆくことになるだろう。
なお読解に際しては会場でのアーティストトーク動画も参考にしている。
◆room1_勝又公仁彦
勝又公仁彦は本展示の企画者であり出展作家である。田中和人と2人で展示する「room1」では、主に「絵画」との近接や重合、交錯といった試行に満ちている。他領域の表現形式・手法にどこまで染めたら写真は「写真」であることの自明性を失うのだろうか。あるいはそれもまた「写真」の変種としてカテゴライズされ領域をまた一つ拡げていくことになるのか。
2人の作品、特に壁面に掛かった勝又作品は、詳細な解説なしで観たならば「絵画展」と見なすに違いないだろう。私は2018年、同会場で「Right Angle」展を鑑賞しており、無機質な立体(建築空間)を平面へと相転移させた抽象絵画的な写真作品であることを了解済であるが、それでも今回の展示物を見渡して、これらは絵画としか思えずわりと混乱していた。
前作「Right Angle」は建築物内の線(面)が収斂する角の部分を写した、抽象度の高いビジュアルを有し、白~灰色で色味とトーンが揃えられ、形式も縦長で揃えられていたこともあり、それらは抽象画のフォーマットを踏まえつつもコンセプチュアルな「写真」のシリーズとしてあった。
だが今回の展示では一変してカラフルかつ小ぶりな作品が、正方形(ひし形)となって多数散りばめられており、色味の鮮やかさ、コントラストの強さといい、表面の塗りの質感といい、密集・配列具合といい、抽象「絵画」そのものであった。トークで知ったが、これらは撮影した写真データをカンバスに焼き付けており、上から色を塗ったり、カラフルな壁面や角を被写体としたもののようだ。



この作品群が悩ませるのは/問いかけるのは、どの線、面、色が元の「写真」で、どこからが後付けで塗られた「絵画」なのかが判別困難であるということで、それはそのまま写真と絵画を明確に分割することの困難な領域を示していると考えられよう。
だがそもそも、カンバスと色(塗料)の組み合わせ、平面性、像(被写体)の不在、などはまさに抽象絵画ということになろうが、その図像を描いた動機、その図形は何を表しているのかという意図に立ち返ると、「元の像がそうだったから」、すなわち被写体の存在とその複写であるという光学的なメカニズムへ帰結する点において、これらは「写真」ということになる。描き手の主観や心情、絵画論、信仰などと別の次元で線と面とが存在している。しかしやはり被写体の後に施される色と塗りによってこれらは「絵画」の領分を越境してくる。
写真か、絵画か、という二百年来の二元論を超えてもっとジャンルレスに見通してみると、この部屋は「色」という次元を見ているのかもしれない。物理なモノとしてこの手で扱えず、文字や言葉のように扱うにも指先―キーボードや発声器官といった出力器官と一体化していない、光によって目から吸収し受け身に応じざるを得ないもの。光の変異体。写真と絵画の両世界が依拠し存在し追求するもの。
作品の一部には光そのものを透過し、屈折し、反射するプリズムキューブや鏡も配されており、写真か、絵画か、という二元論は更に混ざり合い、止揚されゆく。壁に層状になって垂れ下がる色付き半透明のフィルムはその逆で、色自体が光の性質を帯びつつも支持体そのものへ転じながら半物性化した様を思わせる。光でありモノでありそのどちらでもない領域で可能な限り広く値をとりながら姿を変容させる「色」、それを催させるのが写真のポテンシャルの一つなのだと知った。



◆room1_田中和人


room1内の壁でも床でも天井際でも場所を問わず展開(顕現?)する勝又作品に対し、明確に固定されたフォーマットを有するのが田中和人の作品シリーズ《Picture(s)》だ。上下二段に抽象的な色を組み合わせた作品がアクリルに封入され、その縦長の長方形が一列に整列している。
上下二段の作品(上下の二点で一つの作品なので「作品」という単位を分割するのはそもそもおかしいのだが、アクリルの入れ子構造になっていてそれが可能となる)は、上がカンバスに直に描かれたペインティング、下はカラー写真の印画紙を破いて合わされたコラージュである。
やはりここでも絵画と写真の二元論で分離され棲み分けされていた「色」が、一つの枠に収めなおされ、見え方/見方を再考するよう働きかけてくる。
上下で色味の取り合わせはシンクロしている。どちらが先に生まれたのか、オリジナルと参照の主従関係があるのかは定かではない。この色味のパターンの意図、意味、モチーフの有無についても語られてはおらず、塗りとプリントの二人一組となった「色」に向き合う。なおトークでは、作品を作る以前の十代の頃にアメリカの抽象絵画の展示を見て衝撃を受けたこと、その影響はあるだろうが本作にモチーフはないことが語られている。
塗りとプリントは併存していて、どちらも完成形を持たないように見える。不完全というのではなく両者にはそもそものあるべき姿としての正解や目的地がなく、さりとて素材でもない。
これらは「色」、ひいては「光」が姿形を宿されてこちらへ現れたものということになるだろうか。ペインティングは塗料を直接に支持体の上へ塗り付け光の反射と吸収を催し、プリントは光の様々な波長が感光した紙を千切って重ねることでこちらも反射と吸収を行う。絵画と写真がそれぞれに表出するエッセンスを、フレームを砕いて抽出したエキスがこの組み合わせだとすれば、アクリルによる封入と規則正しい展示の型を通じて眼に取り込む鑑賞行為は、絵画と写真に分岐されてしまった「光」を網膜で最初の「一つ」へ混ぜ合わせ還元する。
印象派の筆触分割を、更に大きな領域でメタレベルで推し進めるものとなる。

◆room2_鈴木崇

room2では鈴木崇、多和田有希の2名が展示する。
まず部屋に入って目に飛び込むのは大きな2枚の日本画のような、鈴木崇《Trophies of Rightousness(正しさの戦利品)》は、浅いモノクロで描写された地形の襞のような陰影は、近づいて見てみると全てドクロの図なのだった。大量に果てしなく積みあがるドクロの虚無的な、国なき風景。
room2もまた「写真」の手法や形体を光学的に、物理的に問い、試し、攻めているが、展示が壁に掛けられた平面作品ベースで静的なことと、作家2名の心象、関係性から制作されている。room1が絵画と写真の領域横断(交錯)、色と光といった現象におけるメタレベルへの言及だったのに対し、同じ写真表現のメタレベルの探求でも人間的な心性や動機が基底に働いているところが特徴的だ。
鈴木崇作品は4点のうち3点がドクロをモチーフとし、残り1点も暗室での引き伸ばし器と印画紙への焼き付け機構を模してはいるが血の滴りを思わせ、死や破滅のイメージが前面に来ている。だが匂いはない。肉感や情感とは一線を画したところで、ドクロが積みあがる。
ドクロは作者の所有するレプリカのオブジェである。後に作者本人から「アノニマスな死者」というキーワードをいただいた。




世界中で政情不安や戦乱などで荒れてやまない状況にあり、数知れない人々が死をもたらされ続けている中で、この数年来の思い――何もできないことの無力感も含めて、アーティストとしてプロテスト(異議申し立て・抗議)を行ったのが、本作である。
代表作「BAU」や「ARCA」といった、コンセプチュアルな概念を強く帯びたオブジェを扱う作風からすると、本作は真逆と言うか、極めて実直な情感の表出を行っていたので、鈴木崇作品だと気付かないぐらいだった。
だが、同じモチーフ(一個のドクロのオブジェ)を撮影した図像が延々と転写され、配置と大きさを変えながら繰り返されるところには、砂漠の砂粒を拾い上げて数えていくようなコンセプチュアルな行いを感じる。ザラついたモノクロームの描画は、私人としての感情、表現主義的な見え方を抑制して彼方へと押しやり、複製・転写された像がただただ連続していく。そこに数という抽象性が風景となって現れている。
無数という数の抽象性。死の数の途方もなさに零度の空虚が漂うが、これは今起きている現実のネガであり、世界情勢という情景である。
まるで高度な技量でリアル線描画かと見まがうが、大量に重ねられたドクロの図は「コピー転写」、レーザーコピーで出力した写真イメージをラシャ紙に転写していると、後に作家ご本人に教えていただいた。
作者は「転写・transfer」という言葉よりも「transcend」(超越、越境)の意を推したかったようだ。
画像情報の変換、異なる素材(次元)への転写であることを超えて、それらは画像、写真、転写、データ、頭蓋骨オブジェの複写物、などといった個別の情報から国際的かつ精神的な「状況」へと拓かれることを望んでいる。コンセプチュアルが仕立てる悔悟の祭壇にて自室のオブジェは、私性を超えて世界の状況へアクセスし超越する。

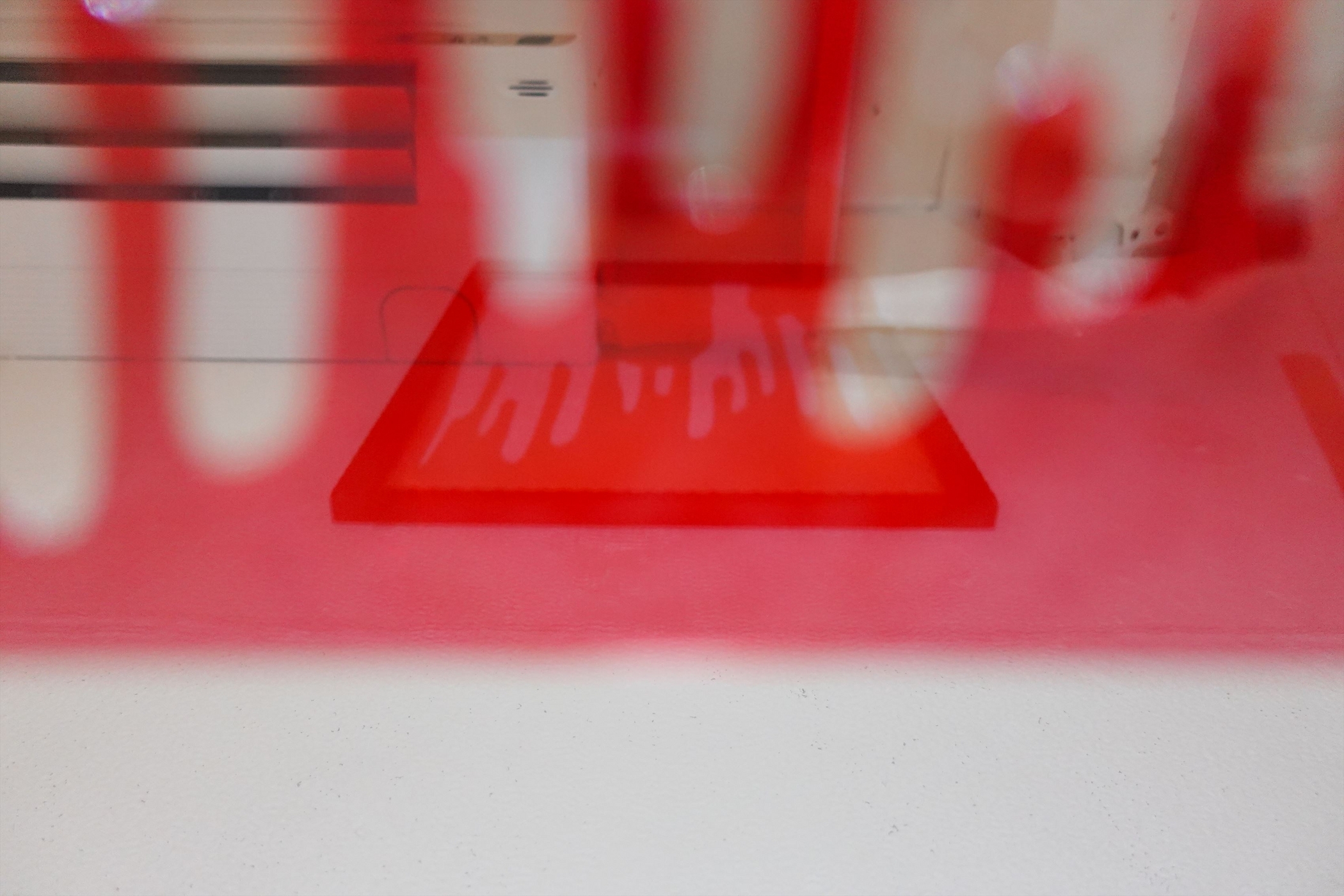

◆room2_多和田有希
写真の面を焼き落とした葉脈のような人の顔、茶碗、耳の彫刻、黒くて大きな紙の塊。
より個人的な思い、個人的な関係性、営みを題材とした作品群だが、作者の経歴やこの4名の枠組みを知らなければ「写真」作品とはダイレクトに結びつかないだろう。
いずれの作品も作者の文脈としては全く正しい。写真のボディを微細に焼き落として(面を抜いて平面をゼロ化するというペインティングの反転行為)、線画と立体物の中間体のように仕上げる手法は昔からのもので、「見るは触れる 日本の新進作家 Vol.19」展(2022、東京都写真美術館)にも だし、器の表面に人物写真を織り交ぜる手法は「写真は変成する2 MUTANT(S) on POST/PHOTOGRAPHY」展(2022,京都芸術大学)でも見てきたものだ。
私も見慣れているというわけではないが、それもまた写真であるということで経験則を積み上げている状態で、その積み上げには作家のプレゼンテーションの確からしさも関わっている。制作動機や制作過程が、なぜこの形に写真を至らしめたのか、と。今回の多和田作品では鈴木作品と同様に個人の思い、関係性が深く関わっていた。



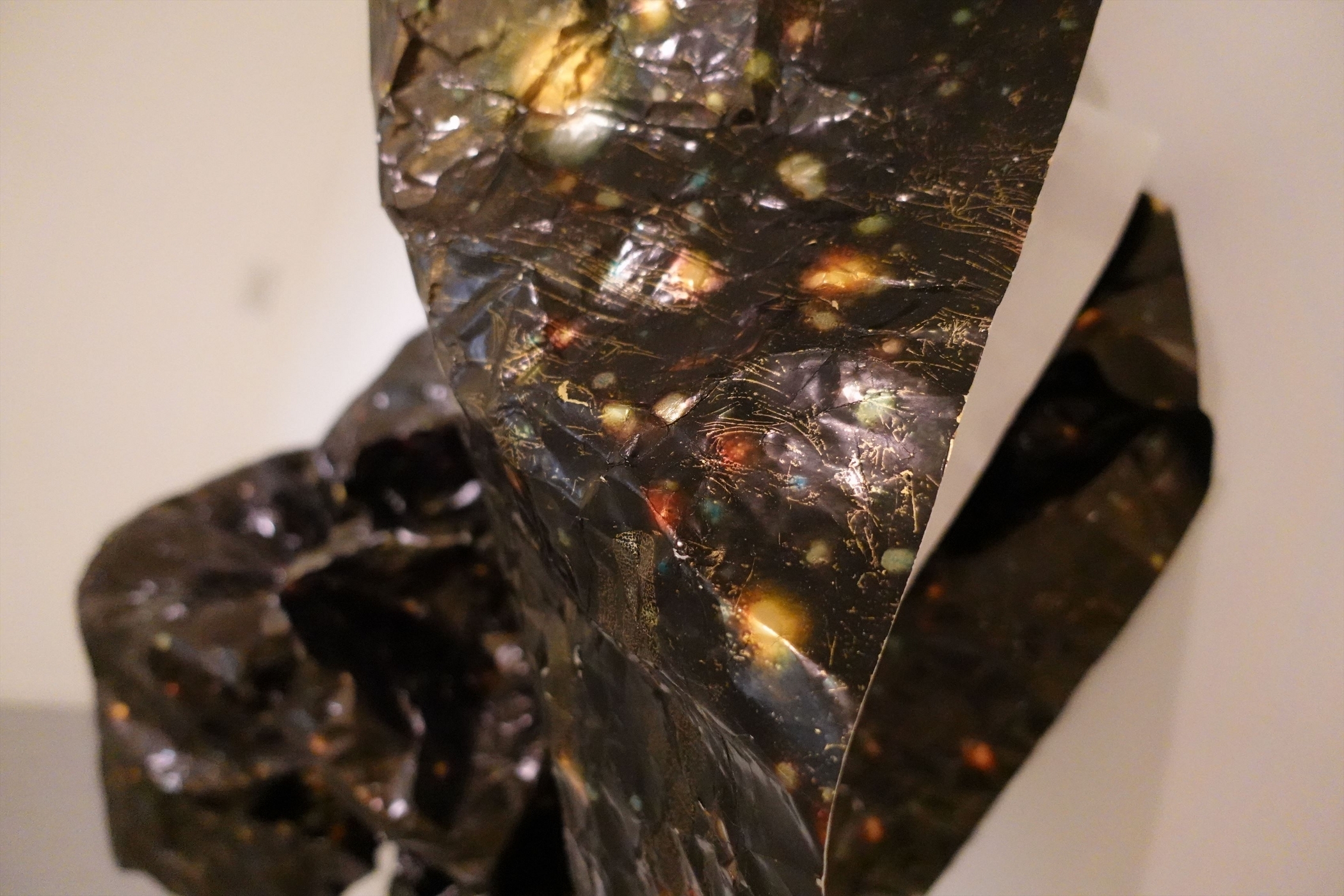

多和田作品は立体的な物性を持ち、従来の「写真」から掛け離れた姿形と質感を有していて、一見すると共通項が掴めないが、直接には触れられない相手への関係性を想像し、写真離れした写真によって形にしている、つまり作者が相手をリアルに直視、記録していなくても成立する写真の形態を模索するものと感じた。
写真の余白が焼き抜かれて顔(目)が浮かび上がる作品《Family Ritual(Phantom Mother-in-law)》は、作者のパートナーの母親の若い頃の顔写真で、早逝したためリアルに会うことはなかったが、古き写真(への関与としての創作行為)を介して関係性を結ぶ。茶碗《青い霊》では作者と陶芸家(福本爪紅)の顔が入れ替えられて架空の人物となっている。大きな黒い紙を折り曲げた立体物《歌う船》はアン・マキャフリーのSF小説のタイトルを引用したもので、星空の写真を立体化しており、私達は宇宙を平面的にしかイメージできないが、それは立体の空間なのでは?と問いかける。
最も写真離れしているのは耳の陶彫《夢の耳》で、写真ではない。ワークショップ参加者が自分の耳の形の陶彫を作ったという作品だ。なので展示品を見ているだけでは写真の要素は全く見当たらない。耳だ。だが制作工程がユニークで、「土はその身に起きたことを記憶している」という着想と「夢の中で写真は撮れない(撮ってもこちらへ持ち出せない)」もどかしさとを結び付けており、土に夢の内容を語り聞かせて記憶させ、後は黙って自分の「耳」を作る、つまり土が音のフィルムのように記録媒体となり、紙プリントのように可変的に立体で加工されるという、まさに写真的な記録・転写と拡張のプロセスを経て作られている。
これらの作品は四角い平面の「写真」に圧縮され折り畳まれた、記録メディア、記憶の語り手としての種々の独自の形態や性質の要素について、部分的に摘まみ上げては浮き彫りにさせて考察を促す。最も写真のメディア性と密に底流を成しているのが作者個人の(人間としての)情感や想像、関係性の「語り」であろう。自分にとって写真とは何であるか、写真が何を想起させるか、写真によって誰かとどういう関係にあるか、等々が語られることで、アナロジーの共振を受けて「写真」なるものが立ち上がってくる。
光学的、視覚的である以上のものが「写真」にはあるのではないかと感じさせられた。
------------------------
はい。面白かったですね。
平らな紙とは異質なものに像をプリントしたり、立体化したり、プリントを焼いたり削ったりするから新しい表現で現代的だということになるのか? というとそれは表現要素、試行の一部であって、思考による接続があるから物理的に遠のいたはずの「写真」が寄せて返して「来る」のだと思います。どの現代美術もそうなんでしょうけれども。
シャーロット・コットン「写真は魔術」のページめくってガン見しててもだめで、こういうリアル実践と作者の言葉と鑑賞体験が化学反応するのを積み重ねないと、たぶん恐ろしく退屈な飛び道具のサンプル集にしか見えない。やはり飛び道具は3次元的に、4次元的に、予期せぬ動きを繰り出すから「飛び」なのであって、そういう写真的拡張の機会は注視していきたいですね。
( ◜◡゜)っ 完。